長年親しまれてきた自転車の交通ルールが、2026年4月1日より大きく変わります。自動車やバイクと同様に、自転車の交通違反にも「青切符(交通反則通告制度)」が導入され、16歳以上の違反者には反則金が科されるようになります。
「自転車だから大丈夫」という認識は過去のものとなり、通勤・通学や日常の買い物で自転車を利用するすべての方が、新しい制度とルールを理解しておくことが極めて重要です。今回は、この青切符制度の概要と、私たちが日常で「うっかり」やってしまいがちな違反行為、そしてその反則金の額について解説します。
🚲 そもそも青切符(交通反則通告制度)とは?
制度導入の背景と目的
近年、交通事故の総件数が減少する一方で、自転車関連事故の割合は増加傾向にあります。特に死亡・重傷事故の約4分の3で自転車側の法令違反が認められており、事態は厳しい状況にあります。
これまでは、自転車の交通違反は全て「赤切符」による刑事手続(検察官による起訴・不起訴の判断、裁判、罰金の納付など)で処理され、有罪になると「前科」がつくことになっていました。
青切符制度の導入は、こうした手続きを簡易・迅速化し、違反者や警察の負担を軽減するとともに、反則金を納付することで前科を回避しつつ、実効性のある責任追及を可能にすることを目的としています。
この制度導入後も、飲酒運転や妨害運転(あおり運転)といった重大な違反行為については、これまで通り赤切符が交付され、刑事手続の対象となります。今回の青切符導入は、これまでの重大な違反への対応を変えるものではなく、軽微な違反(信号無視や一時不停止など)についても、青切符という新しい枠組みで責任追及が明確に課されることを意味します。
対象となる人・違反行為・施行日
- 施行日:2026年(令和8年)4月1日。
- 対象者:16歳以上の自転車運転者。
- 対象となる違反:信号無視や一時不停止といった、危険性の高い「反則行為」として定められた比較的軽微な違反(全113項目)。
なお、警察による指導取締りの基本的な考え方は変わらず、引き続き、違反が認められた場合はまず「指導警告」が行われます。しかし、交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は検挙(青切符または赤切符)の対象となります。
🚨 日常で「うっかり」やってしまいがちな青切符違反事例と反則金
青切符の対象となる反則行為のうち、特に私たちが日常で無意識にやってしまいがちな、または危険性が高い違反行為と、その反則金の額(16歳以上の場合)を見ていきましょう。
| 違反行為 | 違反内容の例 | 反則金の額 |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視したりしながら運転する行為。 | 12,000円 |
| 信号無視 | 赤信号を無視して交差点に進入する行為。 | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止等 | 「止まれ」の標識がある場所で一時停止をしない行為。 | 5,000円 |
| 通行区分違反 | 車道の右側を通行する、いわゆる「逆走」行為。 | 6,000円 |
| 無灯火 | 夜間、ライトを点灯せずに運転する行為。 | 5,000円 |
| 公安委員会遵守事項違反 | 傘差し運転や、周りの音が聞こえない状態でのイヤホン使用。 | 5,000円 |
| 軽車両乗車積載制限違反 | 法律で認められていない二人乗り(幼児を除く)。 | 3,000円 |
| 自転車制動装置不良 | ブレーキがない、または故障した自転車を運転する行為。 | 5,000円 |
| 通行禁止違反 | 「車両進入禁止」など、自転車を含む車両の通行が一律に禁止されている標識がある道路を通行する行為。 | 5,000円 |
特に「ながらスマホ(保持)」の反則金12,000円は、自転車の青切符の対象となる違反の中で最も高額です。スマートフォンを見たり、通話したりしながらの運転は、片手運転や注意散漫により、重大な事故につながる可能性が高く、厳しく取り締まられます。
しかし、あくまで違反の対象となるのは、運転中のながらスマホであるため、信号待ちなどの停車中にスマホを使用することは、違反行為にはなりません。
⚠️ 赤切符(刑事手続)の対象となる重大な違反
青切符の対象とならない、より悪質で危険性の高い違反は、これまで通り「赤切符」による刑事手続の対象となります。
- 酒酔い運転・酒気帯び運転
- 妨害運転(あおり運転)
- 携帯電話使用等(交通の危険):スマホの使用により、実際に事故を起こしたり、交通の危険を生じさせた場合。
- 違反により実際に交通事故を発生させたとき
これらの重大な違反は、懲役刑や高額な罰金が科される可能性があります。例えば、酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。
✅ 私たちに求められる対策
青切符制度は、自転車利用者一人ひとりが「車は車、人は人」という意識を持ち、車両として交通ルールを遵守することを促すものです。
自転車を安全・安心に利用するために、「自転車安全利用五則」を改めて確認し、日々の運転に活かしましょう。
- 車道が原則、左側を通行(歩道は例外)、歩行者を優先。
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認。
- 夜間はライトを点灯。
- 飲酒運転は禁止。
- ヘルメットを着用(努力義務)。
ルールを守り、安全な自転車利用を心がけることが、自分自身や大切な人の命を守ることにつながります。また、悪質な違反を繰り返した場合、自動車等の運転免許の停止処分を受ける可能性もあります。
最新の情報や詳細な違反項目については、警察庁のウェブサイトなどで確認し、安全運転を徹底しましょう。
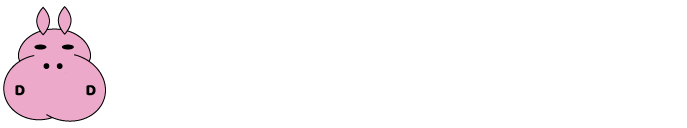


コメント