はじめに:現代の子育てにおける動画との付き合い方
スマートフォンやタブレットが当たり前になった現代。赤ちゃんのぐずり対策や、家事の合間に少しだけ…と、ついつい動画を見せてしまう親御さんも多いのではないでしょうか。「赤ちゃんに動画を見せても大丈夫?」「何歳からなら平気?」そんな疑問や不安を抱えているあなたに、今回は専門的な見解も交えながら、動画視聴のメリット・デメリット、そして賢い付き合い方をご紹介していきます。
赤ちゃんの脳と動画の関係
なぜ「動画は良くない」と言われるの?
赤ちゃんに動画を見せることに対して、否定的な意見が聞かれるのはなぜでしょうか。その根底には、発達途上にある赤ちゃんの脳への影響に対する懸念があります。特に問題視されるのが、一方的な情報伝達と受動的な姿勢です。大人がテレビや動画を見るのとは異なり、赤ちゃんはまだ外界との相互作用を通じて世界を理解し、自己を形成している段階にあります。赤ちゃんは、目の前のものを掴んだり、口に入れたり、音のする方向へ体を向けたりと、五感をフル活用して情報を吸収し、脳に新たな回路を築きながら日々成長しています。しかし、動画視聴は基本的に画面から流れてくる情報を受け取るだけの行為であり、自らが働きかける「双方向のやりとり」が極めて少ないという点が良くないといわれる一つの理由といえるでしょう。
他にも、動きの速い映像や急な音量の変化、あるいは過剰な色彩は、赤ちゃんの未熟な脳に過度な刺激を与えることがあります。これは、まるで幼い脳に大量の未処理データを一気に詰め込むようなもので、脳が適切に情報を処理しきれず、混乱を招く可能性があります。その結果、赤ちゃんの集中力が散漫になったり、落ち着きがなくなったり、夜泣きが増えるといった行動の変化が見られるケースも報告されているとのことです。
- 動画視聴は一方的で受動的な情報伝達で、双方向のやりとりがない
- 過度な刺激により、赤ちゃんの脳が混乱を招く恐れがある
いつからならOK?専門家の見解
では、具体的に「いつから」動画を見せても良いのでしょうか。この疑問に対して、多くの専門機関が明確なガイドラインを提示しています。その一つが日本小児科医会が提示する見解です。日本小児科医会では、2歳未満の赤ちゃんには、テレビやDVD、スマートフォンなどの動画視聴を原則として推奨していません。同じように世界保健機関(WHO)も2歳までは動画視聴をさせることを推奨していません。対して米国小児科学会は、1歳半までは動画視聴を避けることを推奨しています。
その理由となっているのが、乳幼児期が脳の基礎が作られる極めて重要な「ゴールデンタイム」であるためです。この時期に最も必要なのは、親との温かいコミュニケーションや、身の回りにある様々なものに触れ、五感を使い、自ら発見する体験です。例えば、絵本の読み聞かせでは、親の声の抑揚や表情、指差しなど、多様な情報が同時に赤ちゃんに伝わり、言葉だけでなく感情や非言語的なコミュニケーション能力も育まれます。
さらに 日本小児科医会は、「子どもとメディア」に関する提言の中で、2歳未満の視聴を推奨しないだけでなく、2歳以降の子どもについても、時間を決めて、親が一緒に見ることを強く推奨しています。これは、ただ漫然と見せるのではなく、動画の内容について親子で会話をしたり、「これは何だろうね?」「どうしてこうなるんだろう?」と問いかけたりすることで、受動的な視聴から一歩進んだ能動的な学びにすることができるからです。同じように世界保健機関と米国小児科学会は2歳~5歳の子供には1日1時間以内の動画視聴を推奨しています。
したがって、赤ちゃんの脳の発達段階を考慮すると、特に2歳未満の時期は動画視聴を極力避け、もし見せる場合でも時間制限と親の積極的な介入を伴うことで、親と子供がコミュニケーションをとる機会とすることが可能となります。
- 脳の発達のために2歳未満の動画視聴は極力避ける
- もし動画視聴するときは、親と一緒に見て動画の内容について会話をする
動画視聴のメリットは?
とはいえ、育児の中で仕方がなく動画視聴に頼る時間があるのも事実。じゃあ赤ちゃんに動画を見せることのメリットはないのか。そこについても解説していきます。
メリットの一つが知育的な効果です。例えば、手遊び歌などの動画は、リズム感を養ったり、言葉のリズムを覚えたり、身体の動かすきっかけにもなります。また、動物や電車、車など物の名前や色を学ぶ動画など、年齢に合った質の良いコンテンツを短時間だけ利用することで、子どもの好奇心を刺激し、学びのきっかけになることもわかっています。注意としては、動画が直接的に知能を高めるというよりは、子どもが何かに興味を持つ「きっかけ」としての役割を果たすと考えておくのがいいでしょう。なので、動物の動画を見た後に実際に動物園に行ったり、電車の動画を見た後に実際に電車に乗ったりと、動画で得た情報を現実世界と結びつけることができ、より深い学びに繋がり、動画視聴の価値が向上していきます。このように、動画はあくまで「道具」であり、使い方や状況を限定すれば、学習の導入部として機能することが期待できます。
- 子どもの好奇心を刺激し、学びのきっかけになる
赤ちゃんに動画を見せる際の3つのルール
動画なしに現代の子育てを行っていくのは至難の業といえるでしょう。とはいうものの、赤ちゃんの健やかな成長を最大限に守るために、動画を賢く利用するための3つの重要なルールをご紹介します。
1. 時間と年齢を守る
最も基本的なルールは、動画を見せる時間と、子どもの年齢に一定の制限を設けることです。赤ちゃんの脳は、私たち大人が想像する以上に繊細であり、急速な成長を遂げている時期だからこそ、不必要で過度な刺激は避ける必要があります。
具体的には、2歳未満は動画視聴を極力避けるのが基本になります。そして、2歳以降の子どもについても、1日あたりの視聴時間は最大でも30分~1時間以内に留めてあげるのがいいでしょう。また、生活習慣を乱さないためにも、食事中や寝る前の視聴は控えることが大切です。例えば、食事中は家族との会話の機会を増やし、食べ物の感触や味に集中させることで、五感を育む大切な時間となります。寝る前の動画視聴は、脳を興奮させ、睡眠の質を低下させる原因にもなってしまいます。
2. 親が一緒に見る
動画を見せる際に最も重要なのは、ただ子どもに画面を「見せる」のではなく、親が「一緒に見る」ことです。この「一緒に見る」という行為が、動画の一方的な性質を双方向のコミュニケーションへと変え、より教育的な価値を生み出します。
子どもが動画を見ている間、親が隣に座り、一緒に画面を見つめ、声に出して反応することで、動画は一方的な情報伝達のツールから、親子の間に新たな会話や学びのきっかけを生む「媒介」となります。これにより、子どもは画面の情報を受け取るだけでなく、親の言葉や表情からその意味を深め、感情を共有し、コミュニケーションの楽しさを体験することができます。例えば、動物の動画を見ている時に、「あれはなんていう動物かな?」「ワンワンだね!」「どんな声で鳴くかな?」と問いかけたり、動画の中の歌を一緒に歌ったり、ダンスを真似したりするのも良いでしょう。動画に出てくる色や形、数字について親子で話すことで、知識の定着を促すこともできます。また、動画で感情表現が豊かなキャラクターが出てきたら、「この子、今どんな気持ちだと思う?」と尋ねることで、子どもの感情理解や共感性を育むきっかけにもなります。このように、親が積極的に関わることで、動画視聴は単なる受動的な時間ではなく、親子で共に学び、笑い、感情を共有する貴重なコミュニケーションの時間へと変わるのです。
3. 質の良いコンテンツを選ぶ
赤ちゃんに動画を見せる際に、どんなコンテンツを選ぶかという「質」の問題は、量や時間管理と同じくらい、あるいはそれ以上に重要になってきます。
世の中には無限の動画コンテンツが存在しますが、中には赤ちゃんの脳にとって刺激が強すぎたり、教育的な要素がほとんどなかったり、あるいは不適切な内容が含まれていたりするものもあります。無作為に動画を選んでしまうと、子どもの発達を阻害するだけでなく、不安や恐怖といったネガティブな感情を引き起こす可能性さえあります。そのため、親がフィルターとなり、子どもの年齢と発達段階に合った、質の高いコンテンツを選び出すことが不可欠です。質の良いコンテンツとは、例えば教育的な歌やダンス、物の名前を覚える動画、正しい日本語や数字を学ぶためのコンテンツなどです。NHK Eテレで放送されている子ども向け番組などは、幼児教育の専門家が監修しており、子どもの発達に配慮された良質なコンテンツの宝庫とも言えるでしょう。具体的には、「いないいないばあっ!」や「おかあさんといっしょ」のように、言葉や歌、体操を通じて、自然と学びを促す番組などがあります。また、シンプルなアニメーションで物語が展開されるものや、現実の動物や自然の映像を通して好奇心を育むドキュメンタリーなども良い選択肢です。大切なのは、派手な演出や速いカット割りが少なく、子どもが内容をじっくりと理解できるようなペースで進むものを選ぶことです。
- 2歳未満の赤ちゃんは動画視聴を極力避ける
- 2歳以降の子どもについても、1日あたりの視聴時間は最大でも30分~1時間以内に留めてあげる
- 生活習慣を乱さないためにも、食事中や寝る前の動画視聴は控える
- 動画を見るときは、親が隣に座り、一緒に画面を見つめ、声に出して反応する
- 教育的な歌やダンス、物の名前を覚える動画など質の高いコンテンツを選ぶ
まとめ:大切なのは「どう使うか」
ここまで、赤ちゃんへの動画視聴について、メリット・デメリット、そして具体的なルールを深掘りしてきました。最終的に行き着く結論は、動画は「善」でも「悪」でもなく、「どう使うか」によって、その価値が大きく変わるということです。現代において、動画を子育てから完全に排除することは、現実的ではありません。しかし、だからといって、漫然と子どもに画面を見せ続けることは、赤ちゃんの健やかな成長に悪影響を及ぼすリスクあります。
親が赤ちゃんに対する動画の影響を正しく理解し、利用頻度を管理し、親と赤ちゃんで一緒に見ることで、動画が赤ちゃんの発達を妨げるのではなく、むしろ発達の機会を与えるツールにすることができます。動画に頼りきりになるのではなく、動画をあくまで一時的な道具として位置づけることが重要です。例えば、動画で新しい歌を覚えたら、それをきっかけに家族で一緒に歌ったり、手遊びをしたりする。動物の動画を見た後には、動物の絵本を読んだり、実際に公園で鳥や虫を探したりする。このように、動画で得た情報を現実世界での体験や学び、そして親子のコミュニケーションへとつなげていく工夫をすることで、動画は子どもの好奇心を刺激し、世界への興味を広げる「きっかけ」になってくれます。この意識を持つことこそが、デジタル時代を生きる赤ちゃんたちの健やかな成長を支える鍵となると思います。
最後に
赤ちゃんへの動画視聴に関する悩みや疑問は、多くの親御さんが抱える共通のテーマです。今回ご紹介した情報が、あなたの不安を少しでも和らげ、より自信を持って子育てに向き合うための参考となれば幸いです。
あなたのご家庭では、赤ちゃんや小さなお子さんとの動画視聴について、どのようなルールや工夫をしていますか?「こんなコンテンツを見せている」「こんな時は動画に頼る」「我が家ではこんなルールで乗り切っている」など、ぜひあなたの経験や知恵をコメントで教えてください。みんなで情報を共有し、より良い子育てのヒントを見つけていきましょう。
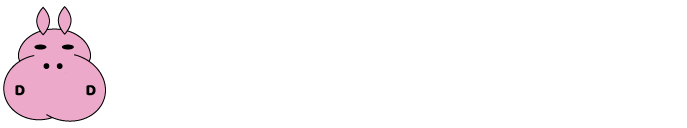
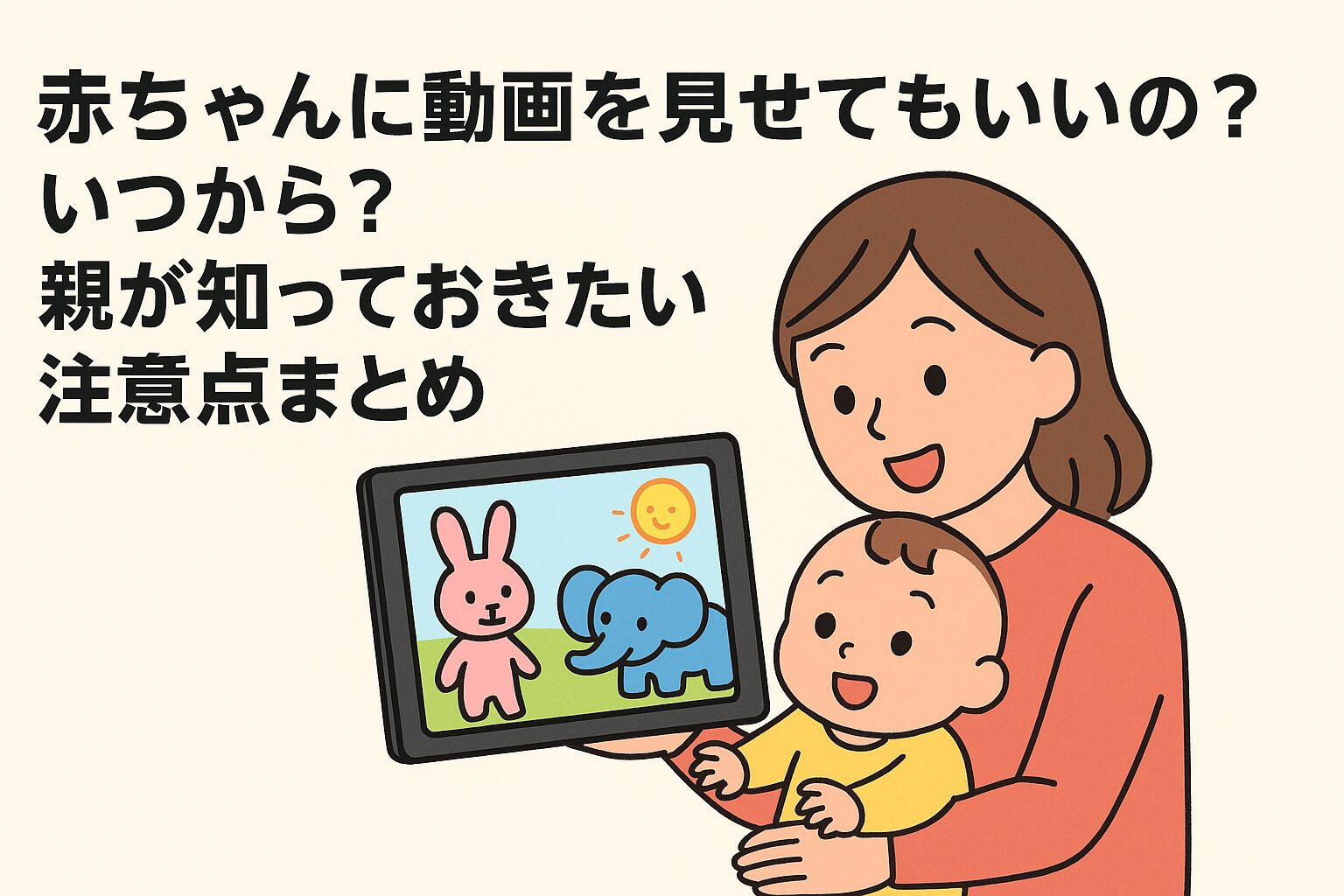

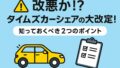
コメント